書評『一生忘れない読書』 -100分で3回読んで血肉にする超読書法- ジョン・キム 著
<引用>
読書の目的は、「視点の転換」にこそある。そもそも普遍的な真実は本には書かれていない。現実は二次元の絵画ではなく、三次元の彫刻なのである。見る人によって、見る角度によって、見え方が異なってくる。ある人にとっての真実も、他の人にとっては真実ではない。人生は数学や物理ではない。いろんな正解があっていいのだ。
だからこそ、大事になるのは「自分の視点」を持つことである。その視点を磨くことが重要になる。
そして読書をすることで「自分の視点転換」が生まれる。読む前と読んだ後に、世界を眺める視点をシフトできれば、その読書は成功したことになる。だから、必ず自分の視点で本を含む世界を眺めるようにする。ここが、スタートラインである。
読書に限らず、テレビや新聞、ネットなどのメディアに接するときすべてにおいてそうであり、どんな目上の人、偉大な人と話をするときにおいても、意識しなければいけないことがあると私は考えている。それは、自分を「脇役にさせない」ことである。自分への絶対的な信頼を持って臨むことである。
そうすると、本を読みながら、自分の頭の中では常に二つ同時に思考が進行することになる。「この著者はこう言っているが、私はどう思うか」を考えるのだ。平行に対話をする感覚で読むのである。
そうしないと、著者の視点が、ただ一方的に入ってきてしまう。単に、脳の中にある情報が上書きされるだけになってしまう。これでは記憶にも残らないし、誰かに語ろうにも単なる受け売りにしかならない。
そうならないためには、自分が何を受け取って、何を捨てるかという取捨選択と、対話を通じて新しいものを生み出すような感覚が必要になる。それこそ、「共同作品」を作るような感覚だ。
これができなければ、読む本によって自分がどんどん変えられてしまう。自分が望む方向に自分の視点を変えるために本を使いこなすという感覚ではなく、本に変えられてしまうことになる。それでは本末転倒である。
自分を作るために本を読むのであって、本に惑わされ、揺さぶられるために読むわけではない。本は、自分の人生に役に立たせるための脇役なのである。著者は家庭教師なのである。むしろ、鵜呑みにしない感覚こそが大切になるのだ。
人生においては、幸せも不幸せも材料は同じだったりする。病気にかかったことが不幸だったのか、幸せだったのかは、その人自身の捉え方によるところが大きい。問題にするのは、実は自分自身なのである。自分が問題にしなければ、それは問題にならない。つまり、解釈が幸せにおいては大きな部分を左右するのだ。最終的には、自分が答えを作っているのである。
だから、本を読むときも、著者が書いたものが正解だと思って読んではいけない。書く人には書く人の自由があるが、読む人には読む人の自由がある。そのコラボレーションによって、独自の答えを作る意識を持つことだ。
それが別の作品を生む。物理的には1冊の本だが、読み手の意識次第で別の共著が生まれる。そんな感覚で本を読んでいくことである。
1. この本はどんな本か?
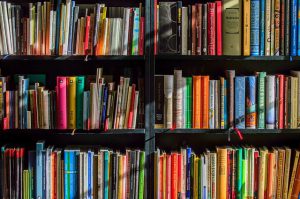
タイトルで分かる通り、読書法の本です。短時間で本を読んで、かつ自分の血肉として内容を忘れないための方法について述べられています。
ですが、それよりも「本」に向き合う姿勢や、「言葉」というものが私たちの人生において如何に大きな影響を持つのかに関する著者の考え方について、より多くの紙面が割かれ、披露されています。そちらの方が重要で、新たな視点を獲得したり、学べることが多いです。
2. 100分読書

まずは、この本で提唱されている読書法について、簡単に触れておきましょう。
・対象となる本はビジネス書や実用書です。(文芸書は対象外だと述べられています)。
・短時間で3回読みます。
例えば、100分で3回読むとするなら、1回目は10分で読みます。2回目が50分、3回目は40分で読む、と時間を設定します。
・1回目の10分で本の目次を読んだりパラパラとページをめくることで本の概要・構造を把握します。
・2回目の50分で、1回目の読書でここぞ、と狙ったところだけを読み、マーカーを引きます。
・3回目の40分で、1回目の読書で掴んだ構造や、2回目の読書で線を引いた箇所などを読みながら、
さらに色を変えてマーカーを引き、自分の感想や意見も本の余白に書き込みます。
だいたい以上の流れになります。
この方法のメリットは、
・自分にとって大事な箇所を複数回、繰り返し読むので記憶に定着しやすい
・100分という制限時間を設けることで、だらだらせずに緊張感を維持しつつ、読書に集中できる。
(読書にあまり長い時間をかけすぎても、結局のところ記憶には残りにくい)
・自分の意見や感情を本にアウトプットしていくので、記憶に残りやすいとともに自分の視点の変化が分かり、内的な変化を実感しやすい
・短時間な取り組みの方が、習慣化しやすい
などといったことが思いつきます。
私は元々自分で買った本に線を引いたり、思い浮かんだことを書き込むことに対して抵抗がありませんでしたし、実践もしていました。(本は使いつぶしてなんぼ、という考え方です)
本書の著者はこの作業を「共著者」になってより良い本を作りあげることだと述べています。著者は読者の役に立ちたくて本を書いているのだから、線を引いたり、メモを書いたりして、徹底的に著者と対話しながら読んでいくことが著者に対する礼儀だと考えている、とのことです。
ただ、この本を汚す方法に対して、抵抗感のある方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、付箋を使ったり、読書ノート(例えば、本文を抜き書きして感想をその横に書き込む)を用意する方法もあると思います。
あと、著者の考えでは、全ての本は自分に対する「手紙」であり、読まれるのを今か今かと待ち焦がれている。本の余白は著者に返信するための「便箋」だとも述べられています。そう考えれば、本に書き込みを行うことに対する意識も
変わってくるのではないでしょうか。
いずれにしても大切なことは著者の考えを受けて、自分はどう考えたのか、それをアウトプットしていくことです。
そしてこの読書法においては「短時間で読める、ポイントさえつかめば良い、と決め込む」マインドセットが何より必要だと述べられています。読み飛ばすことへの罪悪感を捨て、8割は読み飛ばし、2割の本質を見つけ出すことに集中する、とのことです。金脈から石や土をかき分けて金を掘り出す比喩で説明されています。
3. 使う言葉の質を高めて自分の未来を創る

本書では、書かれた言葉をただ読むだけでなく、著者と自分とを対話させることで、本を自分の人生の味方にすることができると述べられています。
対話する、とは著者の意見に従うのではなく、自分なりの意見を持つこと。そしてその力は本にメモしたり、書き込んだりすることで鍛えられていきます。
著者は本を読むことを「自分の人生の地図」を作ることであり、書き込みを行うことで、本が「羅針盤」になると言います。
思考力を高めるためには、頭の中でぼやっと考えているだけではダメで、「言葉にしてみる」必要があります。
言語化する、つまり書きだすことで、それまでふわふわとしていた自分の思考が結晶化され、同時に「客観視」することもできるようになります。
本を読んでいると、
「情景が色鮮やかに五感を伴って目の前に浮かびあがるような巧みな描写」、「なるほど!と膝を打つような面白い比喩」、「はっとさせられるような本質を捉えた言葉」などに出会うことがあります。
そういった、自分にとっての珠玉の言葉達に触れる頻度が増えていくと、自分が使う言葉の質、思考の質も高まっていくと考えられます。
例えば、夕陽が西の空に沈んでいく時の暮れる空の色のように、「悲しい」から「嬉しい」という感情の間にも無数のグラデーションがあります。
問題はそれを的確に表せる言葉を「知っているかどうか」。「白」と「黒」の間の「灰色」をどれだけ細かく分割できるか、です。
その本を読むまでの自分が知らなかった、「いい言葉」。「美しい言葉」。「本質を表す言葉」。
読書によってそれらを収集して、自分でも使ってみる。
それによって、自分の基軸、ベースとなる考え方の部分、内面や精神が磨かれていきます。
その結果が、私たちの未来を創ることに繋がっていきます。
最後に、読書が未来を形作るまでの順番について、もう一度整理しておきます。
本を読む→著者との対話(自分の意見をメモに書く)→思考力が磨かれる
→「自分の選択を正解にしていく」能力が高まる
→自分の人生を自分で創り出していくことができる
という流れになります。
本当はもっとご紹介したい部分があったのですが、分量的にとても引用しきれません。
気になられた方は一度、本書をお手に取って頂いて、ご自身の視点をシフトさせてくれる「珠玉の言葉」を探してみて下さい。
この本に関しては、読書法というノウハウ面を知ることよりも、そちらの方に価値があると思います。
4.まとめ

・ただ読むだけでなく、自分の考えをメモすることで、記憶に残りやすくなるとともに、
思考力を鍛えることができる
・制限時間を決めて、本当に大切なポイントを掴むことに集中する方が、
結果として読書から得られるものは大きくなる
・質の高いの言葉に触れる頻度が高まると自分の言葉の質も高まっていく
その言葉が自分の未来を形作っていく